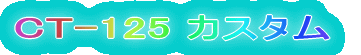
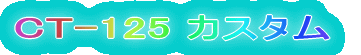
| 画像 | 説明 |
| POSH プレートフォルダー ショボいカスタム。ナンバープレートがひん曲がらないようにするためのもの。 道の駅のカブ仲間からいただいたプレートホルダー CT−125改 本来はつや消し黒だったのだが、車体色に合わせて適当に塗装している。 |
|
| キタコ マルチパーパスバー 意外とハンドルにはナビや電源などが取り付ける隙間が少ない。そのための拡張バー的な意味合いがある。平面部分があって、そこに両面テープにてスイッチが取り付けられて便利。 |
|
| KIJIMA ヘルメットホルダー ここまでケチるか…という標準の仕様。初期型JA55の付属品は工具ではなく、ヘルメット装着用のワイヤと工具箱開閉用六角レンチのみ。これでシートの蝶番部分にヘルメットを固定せよとは非現実的なもの。せめて日本仕様にはちゃんとしたものが欲しかった。社外品でシート横に取り付けるタイプを選んだ。もう一つの方法として工具箱付近に取り付けるタイプもあるが、サイドに荷物が来る場合は実用的ではなくなるためシート横を選択。ビミョーにヘルメットの取付取り外しはしにくいが…仕方ないというところ。 |
|
| SP武川 スポーツマフラー マフラー交換はヤンキーのすることだと信じているので性に合わず今まで一度もしたことが無い。が…CT−125はあまりにも非力であり、このマフラーは低速を犠牲にすることなく1馬力UPするようだ。たった1馬力だが非力な中での、特に中速域での1馬力はとてつもなく大きく見えたので買ってしまった。 純正のヒートガードが取り付けられコケた時にもマシなのと、マフラーを交換してヤンキー改造っぽく見られないのが良い。鉄製は錆びやすいのか、現在はステンレス製のものに変わってしまっているがお値段も高くなっている。当時は4万を切る値段だったのでお買い得だった。政府認証だが音は少々ウルサくなって耳障り。アップマフラーではなかったらマシだったろうに。エンジンブレーキがやたら効くし、減速時にたまにアフターファイアーが鳴るのは仕様なのか?? 馬力が上がったのかどうかは全くの謎。 ※純正ヒートガードは意外とお高くて1万円を越える価格。お手軽に交換という訳にもいかない |
|
| SP武川 ローダウンリアショックアブソーバー(40mmダウン) 初期のシート高は800mmである。さらに股を開いた感じで乗るのでそれ以上に足つきが悪く感じる。乗っていて大変不快なところ。軽いカブだからと言ってコレは酷い。オフ車っぽくしたいところなのだろうが実用性は極悪非道というところ。ショック交換とフロントフォーク突き出し(20mm)で対応した。カブのステキなところは、何かみつけたら気楽にターンして行けるところ。止まって足をベタベタついて気軽にターン(やバック)できるのは どれだけステキなことか。この足つき性に関してはユーザーでも不満が多い点ではあるが、道の駅で出会ったハンターカブでシートの交換をしたものは見たことがあるがローダウンは意外や少ない。シートを交換すると、ただですら小型なので窮屈に足が曲がるのがもっと酷くなるので低身長の方以外はお勧めできない。 ローダウンするとメインスタンドがとっても重くなる。そして立てた後もタイヤが地面よりかなり離れるため、後ろが重いとかなり後ろに傾斜して(フロントが浮いて)停まる。純正サイドスタンドも使用不可になる。 JA55には無いプリロード調整がある…が、工具は別売りというのがケチ臭い。見た目も純正より細く、コレで本当に大丈夫か?な外観。お安いのは良いが通常カブとの共用?部品をやめて、高くても良いからもうちょっとステキなサスにしてくれたら良いのにと思う。 話しは変わるがサスを外したカブはオフ車みたいでカッコイイ。CT−125くらいはプロリンクにしてもいいと思うのだが…。 |
|
| SP武川 アジャスタブルサイドスタンド 40mmローダウンとセットが必須なもの。コレをやらないとサイドスタンドが起きすぎてバイクが立たない。ある程度自由に長さが変更できるので、停めた時の角度が自由に選べるのはステキ。標準でも欲しい機能だと思った。ただし、接地面積は純正並みなのでキャンプ場などではめり込む。 社外品の面積拡張の部品は純正をターゲットにしているので、取り付くかどうか不明。怪しげな汎用品を買って取り付けたが、スタンドを立てたり払う時にバイクを完全に直立させないとひっかかるのが難点になった。 |
|
| 中華製 シフトガイド シフトペダルのシャフトが片持ちで長く出ているため、シフト時にたわむことでフィーリングが悪化する…らしい。これをマシにするためのものが日本製で出ているが、それのパッチものをAmazonにて購入。フィーリングが改善されたかどうかまるで謎。 |
|
| デイトナ バイク用 スクリーン CT125 ウインドシールド RSシリーズ ロング クリアー 16885 これがあると無いとではまるで違う。ヘルメットの下側付近までの風が当たりにくくなる。両腕に風は当たるが、上半身に当たる風が弱くなって感じにくくなる。ライトから上の部分のすきま風に文句を言う馬鹿もいるが、完全に防ぐには昭和のヤンキーバイクに着いていたヤツでも付けろという感じ。十分にコレで実用的。冬場はとてもありがたいし、雨の時もカッパの浸水が弱くなって実用的になる。もはや無いと辛いレベル。が、夏場は暑すぎて困ることもあるので悩ましいところ。 付属のパイプバーにスマホを取り付けていたが、雨の時にもほとんど水滴がかからなくなって助かっていた。が、年寄りの私が悪いのですがスマホと目が近すぎて老眼では確認しずらくなって遠い場所に移設した。 |
|
| デイトナ バイク用 スクリーン CT125 ウインドシールド SSスモーク ロングタイプは夏には風防効果が裏目に出て暑すぎる。ステー部分は共通で短いスクリーンが出ていたので夏は交換して使っている。無いと辛いがありすぎても夏の困るシールド長にはちょうど良いと思う。残念なのがスモークタイプになっており、ヤンキーっぽくビミョーに見栄えが悪いのが難点。 |
|
| ナックルガード(汎用品) Amazonで2000円ちょっとで買った中華の品。これが無いと真冬のグリップヒーターの効きがとても悪く実用的ではなくなる。また、雨の日も雨粒が手に当たらず非常に快適。真夏はさすがに暑いので取り外しているが、それ以外は必須のアイテム。 |
|
| ハンドルカバーYAMAMARUTO 有名老舗メーカーから出ているハンター&クロスカブ専用品。ピッタリ過ぎるという感じで窮屈だが見栄えは割と良いと思っている。グリップヒーターと組み合わせると最強になる。真冬の雪が降る環境でも、真夏の半切れグローブでヒーターレベルも真ん中ほどでもってしまう。が、ピッタリ過ぎて手の抜き差しがちょっと抵抗がある(かなりカバー自体が動いてしまう)。ナックルガードの透明部分を外したステーを入れることによって固定されてマシになった。 |
|
| エンデュランス パーキングブレーキ カブの遠心クラッチは、ギアを入れた状態でエンジンを止めると前へ進む方向にはロックがかかる。が、バックにはロックがかからず動いてしまう。カブプロではリアの(機械式)ドラムブレーキをワイヤーでロックするパーキングブレーキがあるのがうらやましい。ちょっとビミョーではあるが、フロントブレーキレバーをロックすることによってフロントディスクブレーキをかけてパーキングブレーキとするのがコレ。レバー根元に金具を挟むだけなのでやや心許ない。かけるときはブレーキを握りノブを押すだけ。解除はブレーキを握るだけなので楽。 とりあえず、何もしないよりはしっかり停まるが完全にロックではないので完全に信じて良いという訳でも無さそうだ。が、無いよりずっとマシで地味にありがたい。 |
|
| 旭風防 レッグシールド ハンターカブのスタイル上仕方のないところだがレッグシールドが無い。若い頃はオッサン臭くて嫌いだったが、その威力を知ってしまうと無いと辛い装備。格好はとてもビミョーだが、割と高いレベルで再現したものがコレ。お値段も許せる範囲。そして、なにより良いのが取付と取り外しはたいして難しくないというところ。さらに、本体は立体ではなく完全な平面上になるので使わない時の収納もとっても楽。私は冬の寒いときにのみ取り付けて使っている。使っている人がほとんどいないこと、見た目が自作っぽく見えるのか、道の駅などでは結構な人気者になれる。老人には大人気で興味をとても引いている。まず自作かと聞かれることが多い(いきつけのバイク屋の社長にすら言われた) 冬の寒い日、ツーリングで雨の日には無いと辛い装備だ。レッグシールドは純正でも考慮して欲しいくらい。 |
|
| センターキャリア なぜかJA65にはあってJA55には純正品が無い。Amazonにてタイホンダの純正?として扱われる品を買ってみた。ここに荷物を積む気は全く無く、乗り降りするときに、うっかりカバーを蹴っ飛ばしてキズを付けるのを防止するために付けている。それでもやっぱり時々キャリアをかすってしまう。これを取り付けるとバッテリーへのアクセスが面倒になるので付けたくは無いが仕方ない。 |
|
| マフラーガード Amazonにて謎のタイ製?を買ってみた。CT−125のアップマフラーにはマフラーガードが着いている。コケた場合にもガードを交換するだけでOKという親切設計…と思ったのだが、お値段見てビックリ。1万円を軽く越える品だった。ということでそれよりは少しお安い(キズついたとしても塗るか、ゴムを巻いてごまかせる)ガードを買ってみた。本当にガードできるかどうかは謎。 |
|
| スマホホルダー Amazonで買った自転車用のお安いヤツ。ハンドルバーに取り付けるもの。本格的なものは、とにかくボール部分やスマホクランプ部分が大袈裟でゴチャゴチャしているので嫌い。落下防止は、スマホバンパーにストラップを付け、それをホルダー取付軸にくぐらせて落下を防止する。振動防止も無くお高いスマホだとカメラが振動で逝くかもしれないが、私はカメラを全く使わないナビ専用の電話の出来ないdata専用(防水機能あり)スマホで運用しているので全く問題が無い。 最初は、ウインドスクリーンについていた上の方のクランプバーに取り付けていた。(位置的にはコレが一番かと思う) 次にハンドルバー取付部分と共締めしたクランプバーに変更。目から遠くして老眼に優しい位置にした。 最後にスマートモニター取付をその位置にしたため、マルチパーパスバーへと移設した。走行中に目に入りにくいが、スマートモニターでは操作できないことをするためと、充電目的なので位置的には問題無い(目から遠く老眼にも優しい)。 |
|
| パワーフィルター SPパーツ武川 ビミョーなエアフィルター。なぜか純正比しか性能のUPを表示しない。しかも性能UPも極わずか。お値段はかなりお高い。マフラーの交換で排気デバイスを効率化したら吸気デバイスも効率化したいのは人情。効果は謎だけど買ってみた。良いと思うのは、使い捨ての純正品だと、使い切る前まで使い続けないともったいないので交換しない。でも、この品は自分でクリーニングができて再利用するので、気になったら洗えるのだ。そこが気に入って購入。純正なら15000〜20000kmは使いそう(それなりに黒くなっている)を3000km毎に清掃すれば…効果はきっとあるはず(あって欲しい)…と思っての品だ。 |
|
| MOTP-SPEC SF10-40W A.S.H いきつけのバイク屋の社長推薦。1L4000円弱という、目のくらむようなお高いオイル。カブなら1本で済むので使用してみた。以前は、カブなので鉱物混合のお安いオイルを使用していた。特に問題は感じなかったが、鉱物油は黒く汚れるというので、ちょっとと高い純正のG3に変更はしていた。A.S.Hのオイルは特に汚れにくく、最後まで性能が落ちにくいタイプ…らしい。ちょっとお高いが、3000km毎ではなく4000km毎にすれば交換の手間も減るし(←距離を乗る人には割と面倒なことです)、使用量も1回0.7Lなので使い続けている。 |
|
| OPMID オプミッド CT125 JA55 OP マルチメーター 純正品はモンキーやDAXとほぼ共通なもの。怒りすら覚えるショボい品。小さい上にコントラストが低くて見にくい文字。機能もまるで無い。もはや廉価の極みというレベル。唯一、取付位置に関してはカブやクロスカブより低い(目より遠い)位置にあって老眼には優しかったのが救い。それを補完するのがこのメーター。3万円を切る価格で手に入りポン付け可能なのはステキである。文字が大きくてコントラストも高く見やすい。(が夜間も明るさは一定) タコメーターで気分を盛り上げる。純正では、(他の機種でもそうだが)貧乏くさく、いちいち切り替えが多い表示部分も3段の豪華な表示。時計を常時表示して、距離(積算orトリップ)を表示、そして油温か電圧を表示しておける。設定可能なシフトタイミングで光るインジケーター、設定可能な油温警告、設定可能なオイル交換タイミングのお知らせなど機能満載。そして、停まった時には消えるという、あまり役には立たないが、気分はあるだけマシのシフト表示もある。このメーターも、もはや無いと辛い装備の一つ。 |
|
| ギアポジションインジケータ AIpro OPMIDのマルチメーターのギアポジションはエンジン回転数と速度から演算するものなので停止するとギア表示が消えてしまう。一番欲しいのが停止時のギアのポジションなのに。ということで、演算ではなくニュートラル検知用の接点を交換して機械的にポジションを得るインジケーターを購入。気がつくのが遅れたが…もっと早く買っておけば良かったと思う品。停止時に今が4速なのか、それ以下なのか分からないのが意外とストレスだった。地味だがストレスがかなり減ったと思う。これのステキなところは、ニュートラルが「0」ではなくちゃんと「N」表示されるだけでなくNの文字がグリーンなのがニュートラルっぽくて良い(ギア数は赤文字)。若干お高いが満足度は非常に高い。…というか、最初から付けておけよ…のレベル。 |
|
| スマートモニター/ドラレコ Amazon中華のニコマク ドラレコは最初から付けたかったが良いのが無く二の足を踏んでいた。最近の流行でスマートモニターも気になっていた。夏は暑くスマホが熱くなり過ぎ、ハングアップまではいかなくても電力減のため液晶を暗くされて実質何も見えなくなってしまうことが起きていた。対策としてスマートモニターが有効であるし、ちょうどドラレコ兼用の品があったので買ってみた。お安いときは3万円で買えるという中華の品。不要な衝撃センサーやGPSが無いのもシンプルで良い。さらに凄いのはモニター本体はUSB−Cのケーブル1本瀬接続されているのでハンドル周りの配線がとてもシンプル。他のメーカーも見習ってほしいくらい。本体はスマホ並の薄さなのも良い。マジで他に例を見ないステキな品…だが、1年後なぜか後継もなく終息してしまったのは残念無念。機能的にはとてもフツーで前後ドラレコとAndroidAutoかCarPlayが表示できるというスマートモニター。とてもシンプルで良い。一般にスマートモニターを使うとスマホはハンドルに設置しないことも多いが、電源が必要なのと、細かいナビの設定はスマホ必須なのと、雨雲レーダーや音楽プレーヤーの併用するため必須なので仕方ないところ。暑いときは液晶をOFFにしておけば熱対策もなんとかなる。 |
|
| 【ENDURANCE】 CT125 ハンターカブ JA55 グリップヒーターセット HG115 ホットグリップ/電圧計付/5段階調整/エンドキャップ脱着可能/全周巻き 寒いときには必須の装備。電力を考慮した(と思う)純正の半周タイプとは違って全周。そのおかげで消費電力がとっても高い。純正の全周タイプよりも熱くなる。というより最強(全開)だと熱すぎてコリャダメじゃないかと思うくらい。そうでなくても熱でグリップを固定している接着剤が溶けて回るくらい。(冷えると固定される) 機種専用として右グリップ内側部品と電源もセットでポン付け可能。ヘッドライト内部のコネクターより電源を取るがコレ1つで限界という電力レベル。私はLED補助灯も分岐しているため、ヒューズを5A→7.5Aに変更している。LED補助灯を使用している時はグリップヒーターは中以下で使うようにしている(が、グリップヒーターの温度調整はON/OFFの時間で調整するため、ON=全開時の容量でヒューズを設定しておかないとぶっ飛ぶ可能性が高い) 最近はスイッチがグリップ部分にあるスマートなモノが多いが、ハンドルカバーを併用した場合、状態が全くわからなくなるという欠点があるためスイッチ分離式にしてカバー装着時にも見える位置にスイッチを置いた。普段は電圧表示がされるので電力使いすぎがよくわかって良い。また、電圧低下時のカットオフ電圧も自由に設定できるので純正みたいに設定値が高すぎてアイドリング時にすぐ切れるということも防止できる。 |
|
| AutoGo LEDワークライト 改善版 CREE製 10W LED作業灯 狭角タイプ 丸型 仕方のないことかもしれないが、小型バイクのライトは暗い。最初、夜にヘッドライトを点けた時に、これはポジションか?という暗さだったのが印象的。白熱電球よりも省電力になったのはいいのだが、せめて白熱電球並のW数のLEDにしろよ…と怒りすら覚えた。遠くは照らすが広がりが全くないのがノーマルです。これを補完するためにLED補助灯が各社から出ているがビックリするくらいお高い。Amazonで2個で3000円というお安いワークライトを買った。集光タイプだが、光が漏れて対向車に迷惑仕様になっている気がする。かなり手前の低い部分に配光して設定している。1個で10Wとヘッドライトより電力食っているだけあってか、1個でも純正ヘッドライトより明るい。これを2個付けているのだから手前はもう普通の大型バイク並に明るくて良い感じだ。かなり光軸を下げているが光が漏れて対向車に迷惑かもしれないが…目立った方が事故率も減るので我慢してチョの世界。 点灯実験の様子はシャッター速度と絞りを固定して撮影。上が純正のみ。下が純正+補助灯。純正ライトでは手前がほとんど明るくないのが特に辛い。夜間の山道や田舎道を走るときには必須の装備。 |
|
| シガーソケット 意外とソケットだけの商品が少ない。以前から愛用していたのだが、もう廃番になっていたのでAmazonのマーケットプレイスで購入。単純にバッテリ直でシガーソケットを実現する。キー連動になっていないが、逆にこれが良くて選んでいる。シガーソケット対応の品が何でも使えるのが良いし、バツ直のためバッテリーの補充電にもここ経由で行っているので意外と便利。キー連動と、非連動の2つが欲しい今日この頃。 以前は温度表示可能なUSB5V変換アダプタを入れていた。温度表示が見やすくて良かったが、USB電源が1系統しかないので温度計を別に設置して2系統出力のものを利用している。最初はハンドルに設置したがハンドルカバーを取り付けるときに邪魔になったのでマルチパーパスバーに移設。 |
|
| デジタル温度計(外気温) 意外とバイクに装着するデジタル温度計(外気温)が少ない。シガーソケットに温度も表示可能なUSB5V電源アダプターをつけていたが、電源2系統が取れずに困っていた。 Amazonで、安くて怪しげなものがあったので買ってみた。純正のシガー電源の穴より少し大きいが、ヤスリで少し削ると楽に入る。防水じゃないので雨には注意が必要。光量が低いので明るい日中は見にくいのが難点。 |
|
中華リムステッカー Amazonで2000円くらいで買ったお安いヤツ。CT−125用のものは日本では売ってない。とっても怪しい中華の出品者からの購入であったが1ヶ月くらいして中華から届いた。どうやって貼るんだ?というリムの平面部の幅より幅広いステッカーであり、貼ってみたがやっぱり無理。途中でハサミにてできるだけ細くしてから適当に貼り付けた。シワ多数によりしばらくして隙間より浸水により剥がれること必須。 でも、遠目にはわからないし写真では意外と良い感じで映るので、お値段相応で気に入っている。 |
|
| バイクミラー ナポレオン オフセットホルダー45 ブラックSA-25 タナックス デイトナのスクリーンを愛用している。コレには隠れた欠点がある。というのは、ミラーのネジを利用してスクリーンを取り付けているのだが、このための弊害がある。バックミラーを別の位置に移設しているのだが若干内側に寄っている。このためか、ミラーに映る後方の真後ろ部分が体を動かさないと見えにくい。悩んだあげく買ったのがコレ。ほんの少し外側にミラーをオフセットしてくれる品。これで本当に見え方がわずかに変わってストレスが激減。とても気に入っている。コレを使うか、知り合いから聞いたが、カブプロのミラーが、同様に内側からセットされているため長いものが使われているのでコレに交換するか。いずれにせよ後方確認は安全運転のため必須なので大事にしたいアイテムだ。 |
|
| ミシュラン アナーキーストリート 走行が1万キロを越えた時タイヤも交換した。ミシュランの、なんちゃってアドベンチャー向けの品。サイズが17インチではあるが、純正に比べてビミョーに大きく(太く)なる2.50-17 43Pを履いている。もちろんチューブも対応するものに交換している。ミシュランのWebサイトによると、同サイズのタイヤを履くクロスカブには対応しているが、CT−125は対応の記載が無い。ロードインデックスという荷重指数だが、リアがこのタイヤでは範囲外ということかな?と想像している。JA55でギリギリ、なぜ〜かJA65だともっと厳しい。車重を考えても通常カブとそんなに変わらないのに純正指定は謎。よほど重い荷物を積む人が多かったのか? とりあえず、使用しているがメーターやABSには影響が出てないように思う。 ノーマルタイヤに比べてオンロードでのグリップ感というか乗り心地も上がった気がする。元々CT−125はノーマルカブより普通のバイク感が高かったのだが、さらに高くなった気がした。なんちゃってアドベンチャー用なのでオン:オフが9:1とか言われているが、ノーマルのタイヤと同様、どう見てもオフではグリップしないパターン。ノーマルよりタイヤがたくましく良い感じに見えるのと、なんだかイノウエ…というよりミシュランという高級感?が良い。寿命に関しては…ノーマルより若干減りが早いかも?という感じ。もっとも、お値段もそれほど高くないので自分的にはオフは行かないならお勧めできるタイヤ。 ちなみに純正タイヤを11000kmで交換した。リアはそろそろかな…という感じだったがフロントはまだ半分という感じで残っていた。(北海道長距離ツーリングのため同時交換) 交換後2万キロを走ったが、フロント2万キロ、リア1万キロという寿命だった。 |
|
| RK 428 MRU2ゴールド 純正はノンシールチェーン。カブの割には428と幅の広めのチェーンを使っている。純正は11000kmで交換したが(北海道長距離ツーリングのため交換)、雨の日未使用で注油もしっかりしていたので、ほとんど伸びずまだまだ使えるような気がした。が、北海道ツーリングの様に一気に4000km近く走る場合、残りの寿命が心配なのと、途中で注油や引くことが難しいことからシールチェーンに交換。外側がゴールドのメッキなのはメッキだと錆びによる汚れが少ない??から。交換後、北海道内2000kmで初期伸びを引いたが、その後はあまり伸びなかった気がする。他のカブはチェーンケースという強力な防護があるので許せるが、カバーの無いCT-125ではシールチェーンが必須かも。大型バイク用ほど高いものでもないので交換はアリ。さらに2万キロ走ったがそれほど伸びてなかった。走行距離が3万キロを越えたのでスプロケ交換したかったのでペアでチェーンも再度交換した。これならスプロケとセットで3万キロくらいはもつかも。 |
|
| NGK Moto DX CPR6E 全くの気休めの高性能バイク専用プラグ。イリジウムより少しお高い。効果は全くの謎。長めではあるが1万キロ毎に交換。 |
|
| シートカバー 夏はデイトナのメッシュを使っている。空気が通って尻が蒸れず涼しい…気がする。 冬にメッシュのままだと尻がスースーして寒い。歳を取って頻尿になって下半身が冷えるのも困る。カブ専用のシートカバーをAmazonで買い、中にUSB電熱シートを入れてシートヒーターとしている。電熱シートの下には滑り止めのアルミ反射シートを貼り付けて使用。10W弱で、座ったときは全く感じず、コレは意味が無いかと思うのだが、しばらく走ると10W以上あったら尻が熱すぎてダメだろ…というくらいホカホカして心地よい。既に冬のマストアイテムになっている。 |